子どもが不登校になって10年以上経ち、最近少しずつ自分の感情を落ち着いて観察できるようになってきました。
そこで痛感しているのが、不登校の親が辛さや苦しさを感じる中、子どもを支え続ける難しさです。
今不登校の親は一人で立ち向かっている人がとても多いと思います。
その上、他の家族や親せき、学校や周りの人から責められることもあります。
そんな中苦しんでいる子どもを見て、良い関わりを続けていくことはとてもしんどいです。
本当になってみないとその苦しさはわかりません。
そんな中不登校の親の支援はとても少ないと感じています。
また不登校の親の困ったこと、必要なことに合っていないとも感じています。
今私が不登校の親が必要と思う支援は2つあると思っています。
それぞれ説明する前にそのことについてのツイートを載せます。
①不登校の親の支援で必要な2つのこと。
辛さや不満を吐き出せる場と非難されたり、責められたりせずに良い関わりを学べる場のどちらも欲しかったし、今も必要。
辛いことや我慢が続けば心の余裕やエネルギーが無くなってしまう。
それは気持ちを吐き出し、それをあたたかく受け入れてもらうことが必要だと思っている。
でも気持ちが比較的安定している時はどうしたら良いのかを知りたい。学びたい。
どちらも必要だと感じる。状況によってどちらか選択できるような場があるといいのにな。
それぞれが本当に必要だと思っています。
だけどここがミスマッチしてしまう経験をたくさんしました。
そのせいでせっかくの支援の場で傷ついたり、物足りなさを感じてしまうことも多かったです。
子どもが不登校になったママから相談を受けることも多いのですが、このミスマッチのせいで支援から離れてしまう人もたくさんいました。

自分の対応がいけないと言われ、自信がなくなっちゃった。

気持ちわかりますだけでは解決しない。相談に行っても意味がない。
こんな風に言うお母さんが多かったです。
そのせいで孤独になり、親子で苦しさから抜け出るチャンスが減ってしまうと感じます。
だから私はこのミスマッチがとっても大きな問題と考えています。
行政、支援の人、学校関係者、保護者がそれぞれの重要性を知って、それぞれの場が増え、みんなが必要な支援につながれるといいなと思います。
それぞれがなぜ必要なのか説明していきます。
②不登校親の支援 共感的に気持ちを聞いてもらえる場
辛さや不満を聞いてもらうことはとっても大事。
理由はいくつかあります。
このように辛いことや不安や不満を感じることがとっても多くなります。
特に不登校初期のお互いが混乱の中にいる時はこうなりやすい。
また長期化すれば親への負担が積み重なることで子どもを支え続けることが難しくなる場合も多いです。
また再登校や進学など子どもが外と繋がるチャレンジの時も親は精神的に辛い時期です。
ここでまず一番親が支えて欲しいのはその辛さや我慢を理解してくれること。
不登校の親は今までの子育てや今の関わり方、自分自身も責めている場合も多いと思っています。
そういう時にアドバイスや否定ではなく、

そう感じるのは当たり前のこと。
誰だって同じですよ。
と寄り添って、その感情を肯定的に受け止めてくれるところが必要です。
反対にここでアドバイスや正しい関わり方を伝えられるとどう感じるでしょう?
今は傷を癒す必要がある人にアドバイスや正しい関わりを伝える。
私は何度も経験して、これが本当に危険だと感じています。
何故なら自己否定が強くなるからです。
不登校の親を助けるどころか深く傷つけ、自分にはもうムリなんだと思わせてしまう危険があると思っています。
そこがミスマッチが大問題だと感じているところです。
反対に共感的に聞いてもらうことで
これが不登校の親が子どもを支え続けていくためにとっても必要だと思っています。
③良い関わりを責められたりせずに安心して学べる場
もう一つ不登校の子どもの関わりや必要なサポートを学べる場が必要だと感じています。
不登校の子どもの数が増えているのに、良い関わりやサポートを学べる場は一部の支援に限られているのではないでしょうか?
その原因は
不登校の子どもに対して見守りましょうと言われる方もいますが、私はそれでは足りないと思っています。
それはただ見守っていただけでは消せないほど傷が深いと思うからです。
「不登校見守るだけでは足りない!自信を増やす関わりができる(心理的安全性が大事)」という記事で心理的安全性が必要だと書きました.
ですがその後何冊も本を読むうちに不登校の子どもの傷には更にもっと丁寧なサポートが必要だと感じています。
不登校の子どもが学校で起きたことや経験で受けた傷やトラウマはとても大きな影響を与えていると感じました。
そのトラウマやネガティブなセルフトーク(自己否定や自己嫌悪)がどれだけその子の人生に悪影響を与えるかを痛感しています。
それだけ不登校の子どもに深い傷ができていると私は感じています。
その傷をそのままで社会や学校に合わせることで解決しようとすることは一時的には良かったように見えて、とっても危険と感じます。
それは劣等感や自己否定、自分に対する厳しい基準を持ったままだとなにか良くないことが起きた時に
結果的に心身の健康を害す可能性もあると思っています。
自己否定の悪影響に関しては大事だと思うので、また別記事にまとめようと思っています。
参考になった本を掲載しておきます。
◆
『オプティミストはなぜ成功するか』
起きたことへの自分の説明スタイルが悲観的だと学習性無力感やうつになりやすい。
悲観的説明スタイル→自分に原因がある、ずっと続く、よく起こると考える
楽観的説明スタイル→自分以外に原因がある、一時的、特定の場合と考える
悲観的な説明スタイルを楽観的に変える方法が説明されています。

オプティミストはなぜ成功するか
◆『Chatter(チャッター)―「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法』
この本はネガティブな言葉を自分に話しかけることをチャッターと呼び、チャッターが引き起こす数々の問題とチャッターを制御する26の方法が説明されています。
最後の章にはまとめがあって、「自分だけに実践できるツール」「他の人を支援するためのツール」「支援を受けるためのツール」などに分類されていて、困った時に確認できるので、とても助かっています。

Chatter(チャッター)―「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法
◆『逆境に生きる子たち トラウマと回復の心理学 (早川書房)』
この本はアメリカの臨床心理学者の著者が虐待やいじめ、親の離婚などの困難な状況で育った子どものなかに人並み以上の社会的成功を収める「スーパーノーマル」と呼ばれる人びとが居ること。
その人達が成功の影でどんな心の問題を抱えていたかが書かれている。
私はこの本を読んで、レジリエンス(回復力)があることはとっても大事だけれど、過度のレジリエンスは心身の限界を超えさせ、心身を壊す可能性が高いことを知りました。
またレジリエンスが高い「スーパーノーマル」以外の人も同じようにトラウマを持ったまま生きているのではと想像しました。
この本では最後にメグジェイさんが心身共に無理をしないようにできること、やって欲しいこと、考え方を書かれています。
逆境に合ったすべての子ども達がその後の人生を安心して自分らしく生きることを大事にして欲しいと強く思いました。
これらの本を読んで、
不登校の子ども達も同じように学校で起きたことや経験からできた傷を丁寧に癒し、安心して自分らしく生きる考え方を手に入れるサポートが必要だと感じます。
また劣等感や自己否定はその後の人生で友達との些細な意見の衝突や誤解、仕事での失敗、夫婦の関係こじれなどで自分のせいと感じやすいと思いました。
そのせいで防御的になったり、防御から攻撃的になったり、自信がないせいであたたかな人間関係を作ることが難しくなる場合も多いと感じています。
実際に息子たちは自己否定や自己嫌悪も多くみられます。
またそのせいで人との関係に不安を感じていて、次の一歩が難しくなっていると感じています。
私はこの自己否定や自己嫌悪を取り除くことに今とても力を入れています。
その為に上記の本やトラウマの本を読み、子どもとの関わりや声かけで試行錯誤トライしています。
本当は専門で勉強してきた人、支援の人から学べる場があって欲しいと思っています。
専門の知識が必要なくらい傷が深く、トラウマがあると感じるからです。
でも今はその支援の場や人が圧倒的に足りていません。
今は不登校の人数が多いので、一人一人には難しいと思います。
実際に一人に対してとても時間もかかることだとも思います。
それならばせめて先に基礎知識が学べるような冊子や動画講義を用意して欲しいと感じています。
基本的な考え方や子どもの状態を見る視点、日常でできるサポートや声かけを動画や冊子にまとめてもらえて、不登校に関わる保護者や先生、カウンセラーや周りの人が簡単に手にできるようになるといいなと思います。
子ども達はどんどん成長していきます。
今の時間がとっても惜しいです。
だからベストは目指せなくてもこれだけは絶対知っている必要があるということでもいいので、教えてもらえる場や媒体が欲しいと切実に思っています。


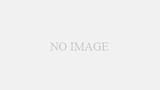
コメント